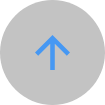今期活動方針
2025年度(第56期)活動方針
「脚下照顧 そして一歩先へ」
基本方針
私たちは、「国民や地域と共に歩む中小企業」をめざして、「自主・民主・連帯の精神」で、「よい会社をつくろう」「すぐれた経営者になろう」とともに、私たちを取りまく「経営環境を改善する」運動体となるという「三つの目的」を理念としています。
私たちがすすめていく同友会運動は、「三つの目的」の実現をめざし、「自主・民主・連帯の精神」で会活動をすすめ、「国民や地域と共に歩む中小企業をめざす」という同友会理念を掲げて、社員とも同友会理念を共有し、さらには国民および全人類的視点に立ってすすめる運動です。
同友会運動は時代とともに評価も高まり、新しい時代に向けて期待も高まっています。その期待に応えていくのは私たち会員一人ひとりです。いかなる経営環境においても経営者の責任を自覚し、人を生かす経営の総合実践により、社員一人ひとりが持つ能力が最大限に発揮される環境を整え、活力に満ちた強靭な企業体質をつくりましょう。企業経営の根幹である経営理念の確立をはじめ、発表から50年経った今でもみずみずしい生命力を持った 「中小企業における労使関係の見解」(労使見解)の観点での経営指針の成文化と社内での共有、さらには社外への発信をすすめていきましょう。そして地域への影響力をさらに高めるために、地域の多くの経営者にも声を掛け、仲間の輪を広げ、豊かな地域社会の持続的発展に寄与していきましょう。
「中小企業憲章」(2010年6月18日閣議決定)では、その冒頭において「中小企業は、経済を牽引する力であり、社会の主役である。常に時代の先駆けとして積極果敢に挑戦を続け、多くの難局に遭っても、これを乗り越えてきた」と位置付けています。私たちはここに誇りをもち、全会の取り組みで、“地域に必要とされる、なくてはならない地域企業”となり、“幸せに暮らせる地域づくりの核となる経営者集団”を目指して成長していきましょう。
この数年、2025年のあるべき姿をめざして策定した「第8次ビジョン」に基づき同友会運動をすすめてきたことを振り返り、そのことを土台として、「京都同友会2030年ビジョン」の策定に着手し、京都同友会と地域社会の輝く未来を展望していきます。
重点方針
経営力強化(強靱な体質の企業づくり)
「労使見解」を深く学び、「人を生かす経営」の総合実践で21世紀型中小企業づくりをすすめましょう
経営指針書を毎年更新し、指針書経営を確立することで、「人を生かす経営」を総合実践し、自社の変革に取り組みましょう。
a) 更新時の自社の立ち位置を明確にするために「企業変革支援プログラム(Ver. 2)」の活用をすすめましょう。
b) デジタル化による業務改善をすすめるなど、生産性の向上に努めましょう。
c) 事業承継、後継者問題について計画的に取り組みましょう。
d) 第9期「人を生かす経営」実践塾を開講します。 (4月~9月に予定)
e) 京都オープンを開催します。 (6月~12月に予定)
f) 第25回 京都経営研究集会を開催します。 (10月28日に予定)
g) 同友会大学を開講します。 (11月~2月に予定)
労働環境の整備や採用活動について社員と共に取り組み、自主性や創造力を発揮できる企業づくりをすすめましょう。
a) 共同求人活動に取り組むなど、働きがいがあり魅力ある企業づくりをすすめましょう。
b) 「共に育つ」を理解し、社員共育活動を実践しましょう。
c) 労働関係法規に適合した就業規則を整備しましょう。
d) 経営環境の激変や突然の自然災害、取引先の非常事態などに迅速に対応できるように「事業継続計画(BCP)」の策定に取り組みましょう。
多様性への対応をすすめ、誰もが働きやすい企業づくりに取り組みましょう。
a) 高齢者・障害のある人々・求職困難者・外国人(留学生)など、地域で暮らす多くの人々の働く意欲と多様な働き方に応える企業づくりをすすめましょう。
b) 就労支援ネットワークの整備をすすめます。
地域力強化(地域づくりと経営環境改善運動)
企業づくりと地域づくりを一体化した取り組みをすすめ、より良い経営環境をつくっていこう
地域の課題を経営課題として捉え、自社の成長と地域の発展を共にすすめます。
a) 地域の実情や課題を深く知り、自社の事業がどのような地域課題の解決に役立つかをしっかりと考えて、地域活性化に取り組みましょう。
b) 地域の歴史・町衆文化などを学び、京都の地域資源を活かした地域づくりに取り組みましょう。
c) 経営指針書に地域づくりの観点を盛り込み、具体化を図りましょう。
調査研究活動をさらに充実させ、企業づくり、同友会づくりに活かすとともに、政策要望や提言活動を進めます。
a) 景況調査(年に2回1-3月期と7-9月期)に積極的に取り組み、その結果やD-コンパス(※)を企業づくり、地域づくり、同友会づくりに活かしましょう。
b) 上記を元に、説得力あるデータに基づき中小企業や地域の活性化に向けた政策要望・提言に取り組みます。
中小企業憲章、中小企業・地域振興基本条例の学習と推進を図ります。
a) 地域経済を支える理念としての「中小企業憲章」の精神を拡げ、各自治体で中小企業振興基本条例の制定に取り組み、これを積極的に活用して地域活性化を進めていきましょう。
b) 行政機関と密な関係性を構築し、政策懇談等に取り組みましょう。各自治体で政策審議・立案に参画することを目指して、中小企業振興基本条例の制定に取り組むと共に、産業振興会議の設置を位置づけるように努めましょう。
c) 中小企業の日、中小企業魅力発信月間における研修交流会を開催するなどして、中小企業の価値や課題、役割を積極的に発信していきましょう。
上記を通して地域コミュニティの活性化をすすめる中心的な役割を担っていきましょう。
各関係機関や他団体との協働で地域経済の持続的な発展に寄与し、誰もが幸せに暮らせるを地域社会づくりをすすめます。
行政機関、金融機関、教育機関をはじめとする関係機関や他団体との協働を積極的にすすめ、地域の活性化を図る事業に取り組みます。
地域経済ビジョン【京都版】の改訂作成にとりかかります。
発表から6年を経過し、さまざまな取り組みも進んできています。これまでの活動を総括するとともに、改めて地域経済ビジョン【京都版】の趣旨を理解し、今後の方向性を考え新たなステップにつながる改定版の作成に着手します。
※D-コンパス
景況調査結果を基に「業界別に」、「生データに極力近い形で」、「会員皆さんの興味関心に沿うように」を主眼に編集したレポートで2024年1-3月期より開始
組織力強化(仲間づくりの輪を広げ、増える・強い組織づくり)
同友会で学び実践する企業を増やします
第8次ビジョンで2025年を展望する目標設定として掲げた対企業組織率7%(2222名)を目指します ※対企業組織率は平成26年度経済センサスから引用
a) 地域企業経営者が抱える課題や関心事に真摯に向き合い、課題解決策が見つかる同友会として新たな会員を迎え入れていきます。
b) 同友会と経営を学ぶ仕組みづくりをすすめ(オリエンテーションの充実をはかります)新会員・入会候補者が参加しやすい企画、早い段階での報告機会づくりに取り組みます。
c) 支部、地域会、委員会、部会の各部門間の連携による会員増強と組織活性化を意識的に図っていきます。
d) 青年部会では「京都が誇るリーダーになろう」のビジョンに基づき京都経済と同友会を担う人材となるため、同友会活動と社業の不離一体の実践をすすめ2030年に会勢888名を目指します。女性部会では「つながる女性部会」を目指します。どんな時も、人を大切にすることを基本とし、部会員や部会員に関わる一人一人の想いを尊重し、信頼と絆を育み、共に学び、成長しながら、未来の私たちの仲間誘いたくなる女性部会を目指します。
支部の活性化を通じて人を大切にする仲間を増やします
a) 長年企業経営をされてきた会員から同友会の本質を学ぶ機会をつくり、すべての会員があてにし、あてにされる環境づくりを行います。また、年齢別・業種別・会歴別・経営課題別等の学びの場を作り、誰もが参加しやすい環境づくりもすすめます。
b) 支部活性の源流となる幹事会の出席率を高め、同友会運動の担い手として支部会員の行事参加率(C数値)や活動実態にも着目し、支部の活性化に取り組みます。
c) 支部例会・支部内の小グループ活動等を充実させ、支部会員の「顔と企業が見える」関係づくりを通じて、すべての会員に会の魅力を伝えます。
d) 幹事を中心に委員会への参加率を高め、情報を支部に共有し活性化に努めます。
e) 支部長は支部運営に責任を持ち、副支部長と協力して支部活性化に取り組みます。
広報・情報化をすすめ、ホームページやSNS等の充実、積極的活用をすすめます
a) ホームページをより使いやすく・見やすくなるようにリニューアルし、会外向けへわかりやすく充実させ会員拡大と会内への発信に寄与していきます。
b) 公式Xアカウント、公式Facebookアカウント、公式Instagramアカウントの活用と充実をはかります。
c) マスメディアとの連携を構築し、会外への周知や会員拡大のために外部発信力を強化していきます。
d) 同友会の情報発信力を高めるために、参考事例となる会員企業の経営報告などの発信をおこなえるように広報委員会が各地域会・支部と連携し情報提供、情報共有をおこないます。
e) 記事内容の質向上を図り、会内外への情報発信力を強化するために、当該委員会にて外部講師を招き研修をすすめていきます。